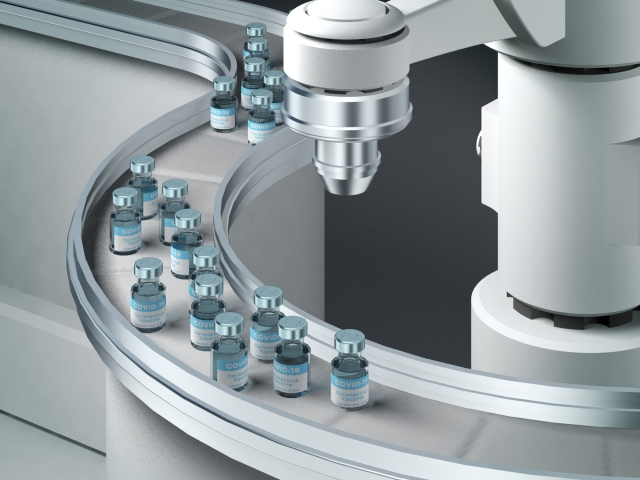アリババ(以下、アリババグループ)という名称はご存知でも、その実態について把握している人は少なくありません。しかしアリババは、今後GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と並ぶ企業になるのは間違いなく、私たちの生活にも関係が出てきます。
ではなぜ、アリババグループは中国を代表する会社となり得たのか。その謎は、アリババグループの経営戦略を紐解くことで見えてきます。
そこで本記事では、アリババグループの経営戦略の解説を中心に、主なサービス内容や中国政府との関係性について解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
アリババとは
まずアリババの概要を簡単に説明していきます。
アリババの歴史

https://toyokeizai.net/articles/-/403485
1999年、創業者である馬雲(以下、ジャック・マー)氏が中国浙江省にあるアパートの一室で「alibaba.com」をスタートさせたことから、アリババの歴史は始まります。
以降、alibaba.comで基盤作ったのち、淘宝網(taobao)や天猫(Tmall)をはじめとして、様々なインターネットサービスを提供してきました。
そして、今なお急成長を遂げており、発展途上真っ只中の中国国内のインターネット業界を支え続けてきた革新的な中国系IT企業です。
2021会計年度のアリババグループの売上高
直近のアリババグループの売上高は、2021会計年度(2020年4月1日~2021年3月31日)では約12兆円(7,172.89億元、※サンアート・リテール統合含む)を超え、前年比41%増と安定した成長を遂げています。
主な事業別売上高としては、中核コマース事業で約10.5兆円(6211.46億元)で前年比42%増、国内小売事業では約8兆円(4736.83億元)で前年比42%増と、右肩上がり。グループ全体の純利益でも約2.5兆円と、盤石です。
※1,000億単位切り捨て
2021年6月12日現在の時価総額ランキングをYahooファイナンスで調べてみると、アリババは9位にランクインしています。

https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/ranking/?kd=4&tm=d
アリババグループの主なサービス
次に、アリババグループの主なサービスについて解説していきます。こちらを把握しておくことで、アリババグループの経営戦略がより理解できます。
BtoBのECプラットフォーム「Alibaba.com」

アリババグループの主なサービス1点目は、Alibaba.comです。Alibaba.comは、製品を売る会社と製品を買う会社を繋げるBtoB向けのECプラットフォームです。今では国際貿易に使用されることもあります。買いたい製品を見つけた会社はプラットフォーム上でメッセージを送付し、交渉を始めます。お互いの条件に合意すると、交渉締結となります。
アリババグループの最初のサービスということもあり、アリババグループの基盤ともいえる事業といえるでしょう。
BtoCのECプラットフォーム「Tmall(テンマオ/天猫)」

アリババグループの主なサービス2点目は、Tmall(以下、テンマオ)です。2008年にローンチしたテンマオは、一般消費者を対象として様々な店舗が出品するBtoC向けのECプラットフォームです。
商品の出品は中国に本籍を置く法人のみが可能で、中国国内におけるBtoC向けECでは55%を超えるシェアを誇る、中国最大のECプラットフォームです。
BtoCの越境ECプラットフォーム「Tmall Global(天猫国際)」
アリババグループの主なサービス3点目は、Tmall Global(以下、天猫国際)です。
名前の通りグローバル版の天猫であり、「越境ECプラットフォーム」といった位置付けをされています。
そのため天猫国際は天猫と違い、中国に本籍がない法人でも出品が可能となっています。
CtoCのECプラットフォーム「taobao market place(タオバオ/淘宝網)」

アリババグループの主なサービス4点目は、taobao market place(以下、タオバオ)です。2003年にローンチしたタオバオは、CtoCを軸としたECプラットフォームで、会員数5億人以上、月間ユーザー7億人以上という莫大な数字を誇る中国最大規模のネットサービスです。
CtoCを軸としていることもあり、条件を満たしていれば個人でも出店が可能です。また、様々なジャンルの商品が出品されていることはもちろん、個人が有する能力やスキルの販売もされています。近年注目されているライブコマースも可能で、中国において誰もが触れたことのあるといっても過言ではない、アリババグループの主力サービスです。
キャッシュレス決済サービス「Alipay(アリペイ/支付宝)」

アリババグループの主なサービス5点目は、Alipay(以下、アリペイ)です。アリペイは、日本でいうpaypayやLINE Payと同じキャッシュレス決済サービスで、中国ではWeChatPay(微信支付)と並ぶ最大規模を誇ります。利用者数は10億人を超えており、全世界の約8人に1人が利用していることになります。中国国内だけでなく、日本でも加盟店数が30万店舗を超えており、世界中で通用する決済サービスといえるでしょう。
食品スーパー「フーマフレッシュ」

https://tamakino.hatenablog.com/entry/2019/09/06/080000
アリババグループの主なサービス6点目は、フーマフレッシュです。フーマフレッシュは、アリババグループが掲げるニューリテール構想(新小売構想)の一角として位置付けられ、デジタルとリアルを融合させた新しい小売店舗として誕生しました。
販売している生鮮食品を調理して食べることができるフードコートの併設や、注文から30分以内の配達対応(3km圏内)など、面白い仕掛けを施した小売店舗という特徴を有しています。さらに、ビッグデータを活用した戦略的な店舗出店や、注文・決済・配送までのオールデジタル化といったように、デジタルを落とし込んだ仕組みも加わり、革新的な小売店舗へと進化を遂げています。
店内の商品レイアウトは、一般のスーパーでは「野菜→魚→肉」という回遊式になっているのですが、これは来店客が価格変動の大きな食材から見て献立を考えられるようにする設計です。一方、フーマフレッシュでは、食材ごとにゾーン分けされされており、通路も広くなっています。
回遊させることよりもスタッフが宅配注文に応じて商品をピックアップすることが優先されています。
ニューリテール構想に基づいたフーマフレッシュは、今後アリババグループの中核事業となることは間違いありません。
その他、アリババグループのサービス
これらの他にも、下記のように幅広いサービスを中国国内を中心に展開しています。
- 旅行サービスプラットフォーム「Fliggy(飞猪)」
- インターネット出前サービス「Ele.me(餓了麼)」
- 動画配信サービス「Youku(优酷视频)」
- ソーシャルネットワークサービス「weibo(微博)」
今では単なるIT企業ではなくインフラ企業へと発展していきました。
アリババグループの経営戦略と今後の方向性
ここからは、アリババグループの革新的な経営戦略を解説します。アリババグループの今後の経営戦略はECプラットフォーム企業からデータ企業への進化が基盤となっていきます。アリババグループは、これまで”アリババ経済圏の構築”を主な経営戦略として事業を展開してきました。
これは、アリババグループの幅広いサービス提供の戦略からも分かるかと思います。
そして、この”アリババ経済圏の構築”に成功したアリババグループは、現在7億人を超えるID(個人情報)を所有しているとされています。しかもこのIDからは、アリババグループ内の様々なサービス利用の情報を獲得できるため、1つのIDから幅広い情報を得ることが可能です。
したがって、この膨大な量、かつ質の高い情報を獲得したアリババグループは、今後の方向性を「ECプラットフォーム企業からデータ企業への変革」へと定め、それに基づいた経営戦略を策定していくと予測されています。
そして、この集めたビッグデータは専門チームの分析・解析を経て、アリババ経済圏への落とし込みはもちろん、アリババ経済圏外への提供も可能とします。例えば、ある一定の地域で経営している小売店舗に対して、「その地域であればこのような戦略を打つべき」というデータの提供が可能となります。実際にこのサービスは、LST(零售通)というプラットフォームとして事業化され、100万店舗以上を会員にすることに成功しました。
これは、アリババ経済圏以外をもデータ活用の対象とし見始めていることの象徴ともいえます。このように、「量と質ともに他社の追随を許さないデータを保有・活用する」ことは、今後のアリババグループの中核戦略となることは間違いないでしょう。
加えて、既に基盤ができていることからも、この情報社会において、アリババグループは世界的を代表する企業の一角を担っていくことが容易に予測可能といえるでしょう。
【最大の障壁】アリババと中国政府の関係性

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201210/k10012756221000.html
一方で、今以上の成長を目指すアリババグループにとって、大きな障壁となる存在がいます。それが、中国政府です。共産主義国家である中国は、習近平国家主席を中心に政府への権力集中を進めてきました。その過程の中で、民間企業として莫大な力を有するアリババグループの存在は、脅威となります。
アリババは2020年12月、独占禁止法違反などで二度も行政処分を受けており、中国政府は、約3,000億円の罰金を徴収したり、アリババグループ傘下の企業の上場を延期させたりと、締め付け強化を進めています。他にも、中国政府の金融規制に対するジャック・マー氏の発言などで、溝は深まるばかりです。
中国ではマー氏は、2020年11月に行われたアリババ香港上場セレモニーを欠席したりSNSの投稿回数が減ったりと、もともと公的な活動が控えられていました。しかし、2021年の年明け早々、イギリスのメディアは、マー氏が2カ月余り公の場に姿を現していないことを「ジャック・マーが失踪した」としてニュースを世界中に発信しました。
このように、中国当局がアリババへの締め付けを強めていることに結びつけて報道されるほど、中国当局とアリババの緊張感は高まっていたのです。
共産主義国家において、政府は経営環境を大きく左右することにもなる存在です。対して、アリババグループは中国政府と並ぶ力を有しているといっても過言ではありません。今後のアリババグループと中国政府との関係には引き続き世界中が注目するでしょう。
まとめ
中国国内だけでなく、今や世界を代表するIT企業となったアリババグループ。その我々では容易に想像できない経営戦略に触れてみて、いかがでしたでしょうか。
今は日本国内においてアリババグループのサービスはあまり親しみがありませんが、日本という大きなマーケットは魅力的なはずです。IT産業が弱いと言われる日本のITサービスの、ほとんどがアリババグループ提供のものになる可能性も0とは言い切れないでしょう。
【参考】
https://strainer.jp/companies/3618/history
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39976720S9A110C1MM8000/
https://netshop.impress.co.jp/node/3241
https://www.cbn.co.jp/archives/25240
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00249/00004/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210410/k10012967011000.html
https://jp.reuters.com/article/ant-group-ipo-suspension-regulators-idJPKBN27M0MT
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-02-27/Q6BB80T0G1L80