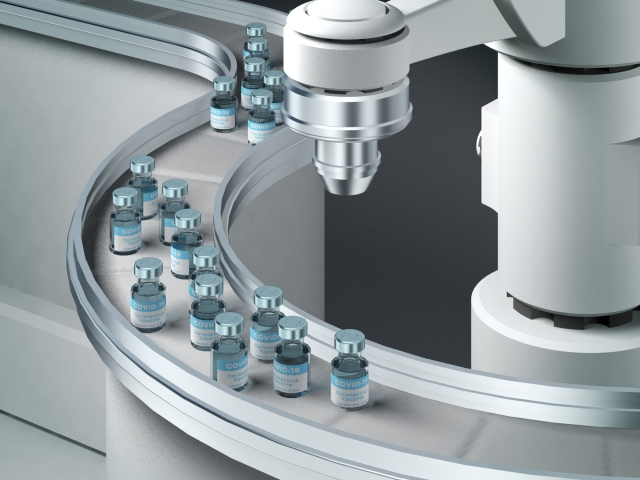人口約14億人を抱える中国は、40年にわたり持続的な経済成長を遂げてきました。
国民1人当たりのGDPが1万ドルを突破するに伴い、化粧品の市場規模も拡大を続けており、2018年時点の化粧品小売総額は2,619億元と中国はアメリカに次いで世界第2位のビッグマーケットを有しています。
新型コロナウイルスにより各国経済が低迷を続ける中、中国では「天猫(Tmall)」や「京東(Jingdong)」といったECサイトが消費を牽引し、KOL(Key Opinion Leader)と呼ばれるインフルエンサーや有名芸能人も続々ライブコマースに参入するなど、インターネットを通じた新たな販売チャネルが定着しつつあります。
この記事では、訪日中国人が減少する中で存在感を増す越境マーケティングでの化粧品マーケティングのポイントをご紹介します。

中国のECマーケットの市場規模
中国のECサイトの市場規模は、2020年には約190兆円になるとも予測されており、世界でも圧倒的な市場規模を誇っています。
しかし、中国のインターネット普及率はモバイルを含めても56.7%と、日本の93.3%やアメリカの95.6%に比べ高いとは言えず、今後は地方都市や農村部での所得の上昇やネット環境の整備に伴い、さらなる市場規模拡大が見込まれています。

では、中国ではどのようなECサイトが人気があるのでしょうか。
ここでは、中国に法人を置く企業のみが出店できる「中国国内ECサイト」と海外法人向けの「越境ECサイト」をご紹介します。
中国国内ECサイト
中国最大のインターネットショッピング・モールとして有名な阿里巴巴集団(アリババグループ)が運営する「天猫(Tmall)」と、京東商城が運営する「京東(Jingdong)」の2大巨頭が中国のECプラットフォームのシェアの8割を握っています。

天猫(Tmall)
天猫(Tmall)は、中国のEC最大手である阿里巴巴集団(アリババグループ)が運営する企業と個人間の取引を行うBtoCのECサイトです。
同じアリババグループが運営する中国国内向けECサイトにCtoCの「淘宝網(taobao)」がありますが、天猫(Tmall)は粗悪品や偽物の販売をなくすため、淘宝網(taobao)よりも高い出店基準(営業許可証の提示や年会費など)を設けることで、消費者が安心してオンラインショッピングを楽しめるECサイトとして中国では人気を博しています。

天猫(Tmall)や淘宝網(taobao)など数々のオンライン取引のプラットフォームや決済サービスを有するアリババグループの2020年度第2四半期(4月~6月)の売上高は1,537.51億元(約2兆3,063億円)に達し、前年同期比34%増と成長を続けています。
新型コロナウイルスへの対応として、中国では1月中旬から徹底した封じ込め策が採られてきました。
こうしたコロナショックによる変化は、消費者のライフスタイルや企業の経営モデルのデジタル化を一層、加速する結果となりました。
アリババグループでは、中国小売市場における年間アクティブ・コンシューマー数は昨年より1,600万人増加し7億4,200万人に達し、ECサイトを通じたオンラインショッピングの利用者が拡大しています。

京東(Jingdong)
EC市場シェアの第2位にある京東(Jingdong)は、自社で仕入れた商品を消費者に販売するビジネスモデルでPCやスマートフォンなど電化製品の販売に強いECサイトです。
自社による物流網の整備に力を入れ、中国全土に広がる物流網を駆使した配送の速さが高く評価されています。

京東(Jingdong)を運営する京東集団( JD.com)の決算によると、2020年第1四半期の純収益は前年同期比20.7%増の146.2十億人民元(1206億米ドル)と、アリババグループ同様、新型コロナウイルスによる巣ごもり需要を追い風に売上を伸ばしています。
海外法人向けの「越境ECサイト」
越境ECとは、国境を超えて行われるECサイト上の取引を意味します。
中国国内にいながら海外の商品を購入できる越境ECは中国で支持され、市場規模は拡大傾向にあり2021 年には越境ECのマーケットは62,938億円まで拡大すると予測されています。
中国では、海外の高品質なブランド品に対するニーズが根強く、新型コロナウイルスの流行による海外旅行の制限も越境ECの増加に拍車をかける結果となっています。

越境ECのマーケットでは、天猫(Tmall)の海外法人向け越境ECサイト「天猫国際(TMALL GLOBAL」を有するアリババグループが、7年連続越境EC市場でシェア1位を獲得してきた「網易考拉(Koala)」を買収したことにより、アリババグループが越境EC市場でも5割超のシェアを握ることになりました。
ECサイトのシェアは網易考拉(Koala)、天猫国際(TMALL GLOBAL)の次に、京東集団( JD.com)が運営する越境EC専門サイトの京東全球網が続いています。なお、天猫国際(TMALL GLOBAL)の2020年4月~6月期のGMV(流通総額)は前年同期比で40%を超える増加となりました。

それでは、越境ECではどのような商品が売れ筋なのでしょうか?
日本貿易振興機構(JETRO)が実施した「中国人が越境ECサイトで直近1年以内に購入した日本製品」についての調査によると、1位が「基礎化粧品」、2位に「メイクアップ化粧品」、3位に「食品」が並んでいます。
同じく、越境ECで重視する項目を調査したところ、第1位が「品質」、2位に「ブランド」、3位に「安全性」が続き、日本ブランドの高品質な化粧品へのニーズが高いことが分かります。

日本人と中国人の美意識の違い
越境ECサイトで化粧品への需要が高いことが分かりましたが、実際に中国の女性はどれくらい美容にお金をかけているのでしょうか。
株式会社ヴァリューズが2018年11月に発表した調査によると、越境ECの利用習慣や訪日経験のある中国人女性が1ヶ月に購入する化粧品の金額は日本人女性の3倍以上で、特に35歳未満の若い世代が化粧品に多額の投資をしていることが分かります。
この理由の一つに、越境ECサイトで単価の高い海外ブランドの化粧品を買う傾向が高いことが挙げられます。
もちろん、中国国内でも多様な化粧品メーカーが産まれており、デパートでは日本を含む海外ブランドの化粧品を購入することができます。
しかし、品質や偽物を買わされる不安から多少金額が張っても「本物」で、効果が社会的に認められている「知名度の高い」ブランドの化粧品を求める声が多いのが現状です。

*出典:マナミナ 日中女性の美容に関する支出金額・ブランドイメージを調査
日本の「化粧は身だしなみ」vs中国の「自然体が美しい」
ところで、日本人と中国人の化粧に対する美意識には大きな違いがあります。
これまで、中国では長らく日常的に化粧をする習慣がなく、日本のように「化粧は身だしなみ」という美意識とは異なり、「自然体が美しい」という価値観をもっています。
2017年の化粧品の販売実績を見ても、全体の50%以上を化粧水・乳液などの基礎化粧品が占めており、日本では20%ほどあるチーク・アイラインなどのポイントメイクの割合も6.74%と、長らくスキンケアを重視したマーケットでした。

このような中国の化粧文化を根底から変えたのが、SNSの発展とそこで活躍するKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれるインフルエンサーの存在です。
KOL(Key Opinion Leader)
中国では中国版インスタグラムといわれる「小紅書(RED)」や中国版ツイッターといわれる「新浪微博(Weibo)」などのSNSやライブコマースが企業のマーケティングやプロモーションに使われており、中国国内の企業はもちろん、日本企業が越境マーケティングを考える上でも切っても切れない存在となっています。
小紅書(RED)
「小紅書(RED)」は2013年にリリースされた中国発の口コミECアプリで、登録ユーザー数は3億人、月間アクティブユーザー数(MAU)は1億人以上に達しています。
衣食住すべての日常生活にまつわる口コミ投稿型のSNSで、日本のインスタグラムのように写真やショート動画を投稿したり、購入した商品のレビューを閲覧することができます。
小紅書(RED)の大きな特徴の一つに、投稿内で紹介されている商品をアプリ内で直接購入できるマーケット機能を持っていることが挙げられます。
投稿で見て気に入った商品は、口コミを確認しながら、そのままアプリ内のオンラインショッピングサイトで購入に進むことができます。ユーザーは若い世代、特にファッションや美容、グルメなどを楽しむ女性に圧倒的な支持を受けています。

新浪微博(Weibo)
「新浪微博(Weibo)」は中国版Twitterと呼ばれ、テキスト、写真、動画、ライブ配信もできるマイクロブログです。
月間利用ユニークデバイス数は4.65億人を超え、中華圏最大級のソーシャルメディアです。メインユーザーは23歳〜30歳で、57%のユーザーが男性という特徴もあります。

小紅書(RED)や新浪微博(Weibo)ではインフルエンサーマーケティングが存在感を増しています。
インフルエンサーマーケティングとは、SNSで大きな影響力をもつインフルエンサーやKOL(キー・オピニオン・リーダー)に企業の製品やサービスを紹介してもらい、消費者に認知をしてもらったり、消費者の購買行動に影響を与えるマーケティングです。
美容系インフルエンサーでは、例えば口紅王子と呼ばれている「李佳琦(Austin)」が有名で、一回のライブで3億円相当の化粧品を売り上げるとも言われています。
中国ではクチコミの信頼度が高く、特にその分野に詳しく影響力のあるKOLが、実際に使ってみたという感想は、消費者が購入を検討する上で非常に重要な情報となっています。

ライブコマース
また、インフルエンサーが商品を紹介し販売する上で、ライブコマースの活用がブームになってきています。
ライブコマースとは、ライブ配信者が商品紹介の動画を配信し、視聴者はリアルタイムに質問やコメントをしながら商品を購入できる新しいEコマースの形で、2015年頃から始まりましたがコロナショックを追い風に高成長を続けています。
ライブコマースを配信するプラットフォームはすでに500個以上ありますが、中でもアリババグループの「淘宝直播(タオバオライブ)」、テンセントの「Kuaishou(快手)」、バイトダンスの「DOUYIN(中国のTikTok)」が勢力を伸ばしています。
大手の「淘宝(タオバオ)」のライブコマースは新型コロナウイルス以降、年初から3カ月で88%増加し、企業が続々参入しています。
越境ECを行う日本企業にとって、中国EC市場で存在感を増しているインフルエンサーを活用したマーケティングやSNSの利用は重要なプロモーション手段になってきています。
しかし、これから越境ECを利用し中国に向けて日本の製品を販売したいと考える企業にとって、どの越境ECサイトを利用するか、中国の消費者に向けたプロモーション・ツールにどのSNSを利用し、インフルエンサーに誰を起用するかなど検討すべき項目は多岐にわたります。
このような悩みを抱える企業に向けて、WEIQでは動画やキャンペーンサイト、公式アカウントなど企業が中国のユーザーに届けたいコンテンツをWeiboやWeChatといったSNSを活用しプロモーションを代行してくれるサービスを行っています。
過熱する中国のEC市場で存在感を出す為のプロモーション手段として利用するのも良いかもしれません。

最後に
SNSの活用やライブコマースなど、新たなマーケティング手法を柔軟に取り込み発展を続ける中国のEC市場は今後、さらに拡大を続けるとの見込みです。アフターコロナで訪日中国人が減少する中、日本企業のプロモーションの仕方も大きな転換期を迎えているようです。
<参考>
NNA ASIA アジア経済ニュース
https://www.nna.jp/news/show/2047566?id=2047566
Alibaba Group Holding Limited
https://www.alibabagroup.com/en/ir/home
経済産業省 電子商取引に関する市場調査
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003.html
マナミナ 日中女性の美容に関する支出金額・ブランドイメージを調査
https://manamina.valuesccg.com/articles/414
WEIQ
https://www.aainc.co.jp/service/weiq/