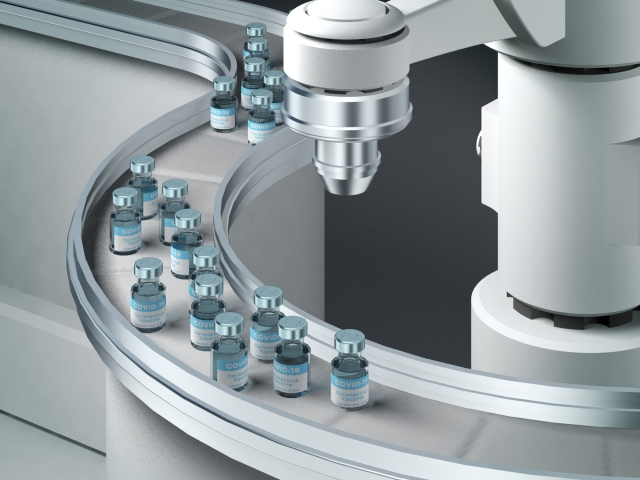中国のSNSは日系企業の中国進出におけるマーケティング戦略において、重要な役割を果たすツールになると言われています。何故なら、中国は口コミ大国であるからです。
しかし、中国では私たちが日常生活で使っているようなGoogleやFacebook、Twitter、InstagramなどのSNSを使用することができません。
これは中国政府がインターネット規制を行い、中国政府にとって損害とある情報が国民へ流れないようにコントロールしているのです。
こうしたことから海外展開に重要なSNSは中国でしか使われていないツールとなるわけなので、私たちが日常使用することはあまりなく、馴染みのないことから、この中国SNSをよく理解する必要があると言えます。
中国へビジネス進出する際の役に立つ情報の一つとしてここでは「中国のSNS まとめ」についてお伝えしていきます。
中国のSNSシェア
2017年に猟豹全球智庫という調査会社が実施した調査に基づくと、簡体字の中国語設定になっているスマートフォンにおいて、週1回以上の利用率が記録されたSNSは以下のとおりです。
- WeChat(微信・ウィーチャット)82%
- QQ 36.4%
- Weibo(微博・ウェイボー) 5.9%
この利用率の調査でお分かりの通り、圧倒的にWeChatが使用されていることがお分かりいただけます。
中国人の40歳より下の年齢層のうち80%以上はこのWeChatのアカウントを持っていると言われています。
この章では中国におけるSNSシェアの高い上位3つがどういうSNSなのかをお伝えします。
WeChatとは
WeChatは日本でよく使われているLINEのようなSNSであり、主にテキストや音声通話、ビデオ通話、写真共有などをグループチャットや個人同士で通信できるアプリケーションとなっています。グループチャットでは最大500人、ビデオ通話は最大9人までの人数制限で利用することが可能です。
その他LINEに似た機能はスタンプのようなキャラクターのスタンプを使うことができる点や、WeChat Payという決済サービスがある点です。この決済サービスについては次の章で詳しく説明します。

QQとは
次に第2位の利用率を誇るQQについてみていきましょう。
QQは2018年時点でおよそ6億4000万人のユーザー数を持っている人気のメッセンジャーアプリです。
上記のWeChatとの大きな相違点はキャラクターなどのアバターを作成できたり、同じ趣味を持つ人が集まれるコミュニティに参加することができる点です。
こうした特徴を持つQQは多くの中国人のメッセンジャーアプリの中ではプライベート用ツールとして使用されています。(一方で先程のWeChatは仕事用ツールとして使われていることが多いです。)
多くの中国人の利用者はこの2つのアプリを使用目的に分けて利用しています。
QQの歴史はWeChatよりも古く、20年以上前の1999年に提供開始されています。
かつてはスマートフォンではなくパソコンでメッセージのやり取りをする際に使われていました。
当時は中国国内での最も一般的なメッセンジャーでしたが、現在もスマートフォンなどの端末も含めて利用されているものの、上記にもあるWeChatには及ばないといった状況です。
Weiboとは
そして次は第3位の利用率があるWeibo(微博・ウェイボー)についてです。
Weibo(微博・ウェイボー)には、新浪微博や腾讯微薄といった、沢山の会社が行っているものがあるため、ここでは「新浪微博」についてお伝えします。
ウェイボーの漢字表記である、微博とは「微」ミニ、「博」ブログという意味合いを持っています。
短文テキストを投稿するTwitterに似た種類のSNSとなります。自分のトップページにタイムラインがつくられ、投稿された内容はフォローに関係なく誰でも閲覧することができます。
他投稿に「いいね」やコメント、リツイートもすることが可能です。
Weibo(微博・ウェイボー)はWeChatと比べて幅広い人々に情報を発信していく場であるとされています。
中国最大のSNSとも言われており、ユーザーは中国を越えた、世界全体で8億人もいるため、中国のトレンドや情報収集には必要不可欠な媒体となります。
WhatsAppとは
こうした中国のメッセンジャーアプリと欧米を中心に世界で最も使用されているアメリカ発のWhatsAppというアプリを比べてみましょう。
日本ではなじみの薄いアプリですが、これにはいったいどんな機能があるのでしょうか?
アメリカ人やヨーロッパ人、アジア人も利用している子のアプリ。
一番の利便性は電話番号とアカウントが直結している点です。
電話番号を持っている人同士かつWhatsAppのアカウントもお互い持っていれば、無料で通話やメッセージを送ることが可能です。
LINEやその他SNSアプリも自分が登録している電話番号と直結させることができるのでどこが利便性があるのかわからないという日本人もいるでしょう。
この利便性の理由は10数年前までは電話しか連絡手段がない欧米では電話料金がものすごく高かったことが挙げられます。
そんなときに電話番号直結型のSNSアプリが出てきて、通常の電話よりも安くコストを抑えることができるとして一気にユーザーを獲得していったのです。
当時日本では電話以外にEメールという連絡手段が主流化していたため、SNS市場の開拓も遅い状況でした。
電話番号と直結型のSNSアプリの需要があまりなかったため、日本では知られていないのです。
一方、中国ではこのWhatsAppも使用が禁止されています。QQやWeChatの方が様々な機能があり、利用目的に応じて使いこなせるため、便利であると言えます。
また、多くの中国人と話したい、もしくは中国の情報をゲットしたいのであれば、WeChatやQQといった中国のSNSアプリを使った方が得策です。
しかし、中国と他国の比較する際の情報を集めたいのであれば多国籍で多くの人々が利用しているWhatsAppを使用する方が良いと言えます。
キャッシュレス比較 WeChat Pay vs アリペイ(Alipay)

このWeChat Payは電子決済サービスはLINE Payとよく似ており、このWeChat Payはキャッシュレス化が進む中国国内で日常的に利用されています。
使い方は客がアプリをインストールしてアカウントを作り、レジにあるWeChat Pay 専用のQRコードをスキャンするだけで決済が完了します。
決済が完了したその時点で客の口座から引き落とされるようになっています。
これは客として利用する際にも便利なサービスですが、この電子決済システムを導入するお店側もメリットがあります。
WeChatの専用アプリを店内のタブレット端末にインストールするだけで、客からの代金支払いが可能となります。
そのため、レジでの会計の際に従来のクレジットカードのように特別な機器を設置しなくても良いので、店のコスト削減にもつながります。
WeChat Pay ともう一つアリペイ(Alipay)と呼ばれる2大中華決済のツールがあります。
アリペイ(Alipay)は世界最大の流通総額を持つオンラインモバイルコマースカンパニーであるアリババ(阿里巴巴)グループの決済サービスです。
中国国内の電子決済サービス業界では約54%のシェアを誇っています。
アリペイ(Alipay)は日本のお店でも導入されており、店頭でもホテルや施設の事前予約などのネット支払いにも使えます。
アリペイ(Alipay)は現在、中国国内市場だけでなく、日本以外にもアジア圏の香港と韓国に市場進出しています。
アリペイ(Alipay)プラットフォームというアジアのQRコード決済アプリを一つにまとめるためのプラットフォームです。
このアリペイ(Alipay)決済プラットフォームではアジア内いおける決済手段をまとめて利用できるようにしていく方向であるため、その計算でいくと将来的に10億人以上のアジア人消費者をユーザーにすることができます。
因みにWhatsAppはWeChat同様にWhatsApp Paymentという送金サービスがあり、インドにおいて実施されるようになっていますが日本では利用不可です。
検索エンジンBing と百度(baidu)

先ほども述べたように中国のSNSでは中国政府が規制をしているため、自由なアクセスができません。
検索エンジンでは、中国で約7割のシェアを誇り、国内最大規模である百度(baidu)というものです。
勿論中国では検索エンジン市場で不動のトップであります。
使い方は基本的にGoogleなどと同じで、調べたいキーワードを入力し、そのキーワードに関連する情報が提供されます。
しかし、百度(baidu)は情報の提供よりも、実際のサービスにスピーディーに繋ぐことを重要視しています。
例えば、乗り物の予約を取りたい時、Googleなどで検索すると、乗り物の会社のHPが出てきて、そこから予約するという形ですが、百度(baidu)では検索すると瞬時に購入・決済ページに直接行くようなシステムになっています。
そのため、私たちが日本でよく使っている検索エンジンよりも、1ステップ速く購入できるのです。
また、中国で近年人気が急上昇している注目度の高い検索エンジンの一つにbingがあります。
このbingはアメリカのMicrosoftがつくった検索エンジンですが、なぜ中国で人気が急上昇しているのでしょうか。
それは、中国国内で利用できる数少ない外国の検索エンジンだからです。
グレートファイアーウォールという名の中国における大規模インターネット検閲システムによって厳しいネット制限が掛けられている中国。2019年1月にはこのbingでさえも一時中国での利用が停止されました。
現在では通常通りに使用可能です。こうした問題があるため、中国人は国内で利用可能な海外発の貴重な検索エンジンとして認識しているため、人気が急上昇しているのです。
Tmallとは

「天猫」(Tmall)とは、アリペイ(Alipay)と同じくアリババグループが作ったオンラインショッピングモールです。
日本では「テンマオ」と言われることもあります。
開設は2013年で、中国市場のB to C-ECシェアでは57.7%と半数を超え、トップを誇っています。
2016年時点での年間流通総額は約22兆円と考えられています。
世界的に有名なAmazonでさえもこの総額は約16兆円と推定されているので、それをも上回る規模であります。
このシェア率が高い理由の一つは、中国内で高い信頼度があるからです。
中国では偽物や非正規品の流通が相次いで問題になっていました。
現在でも中国国内全体ではそうした問題は多々ありますが、Tmallでは世界的に有名ブランドやグローバル企業が出店している関係もあり、非常に厳しい審査がされています。
具体的には、中国で正式な営業許可証を持った法人しか出店できず、さらに商標登録証や販売権利証といった正式な書類を提出した後も、3か月ほどの審査機関があります。
こうした徹底的な審査によって中国本土からの信頼度を高めていき、現在の市場シェア率に至ります。
まとめ
今回中国進出において重要な情報収集などのツールになる現地のSNS事情についてみてきました。
中国はSNSに政府から厳しい制限をかけられているからこそ、様々な外国企業のSNSを使うといった分散がなく、国民の市場が集まり、中国独自のSNSが発展して世界にまで市場を広げていく力をつけたということが分かります。
今回見てきた中国のSNSを使用用途に分けて使って情報を十分に収集し、中国へのビジネス進出・展開を行ってみてはいかがでしょうか。