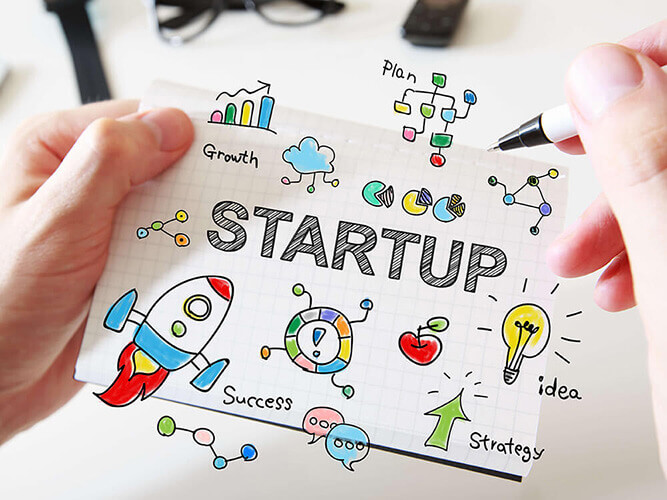「IoTプラットフォームの企業やサービス」と聞いてどのような名前を思い浮かべますか?
下記の相関図で赤枠で囲まれている「エコシステムを持つユーザー系ベンダー」の製品については、現在、シーメンス、GE、日立の競争が激化しています。

下記はエコシステムを持つユーザーベンダー系の2強と呼ばれるSIEMENSとGE、その後を追う日立の、2012年における売上高と営業利益です。

https://toyokeizai.net/articles/-/16430
8年経過する中で、この3社の動向は変わってきています。
2000年代から、SIEMENS(シーメンス)は長年主力であったガスタービン事業のシェアを減らし、ソフトウェア会社の買収を本格化してきました。
2016年から、MindSphere(マインドスフィア)の展開も開始し、SIEMENSはGEを追い抜くかもしれないとも言われています。
一方日本の巨大コングロマリット企業である日立は、東芝やシャープの不振とは対照的に、米GE、独SIEMENSと肩を並べようとLUMADA(ルマーダ)を強化しています。
ここでは、IoTプラットフォーム企業のシーメンス、GE、日立それぞれの企業のサービスや、今どのような動向を示しているかについてお話します。
※本記事は各社のオープン情報を中心にまとめております。
アメリカのIndustrial Internet とドイツのIndustry 4.0
産業界において「ものづくりデジタル化」への取り組みが進んでいます。
米国では「産業のインターネット」を意味する「Industrial Internet」、ドイツでは「第4次産業革命」と呼ばれる「Industry4.0」が推進されています。
アメリカの「Industrial Internet」では、対象は製造業以外にも広がります。
エネルギー、ヘルスケア、製造業、運輸、公共、の5つの領域において、GEを始めとし、Intel、Cisco、IBM、AT&Tが中心となって普及を進めています。参加は、アメリカの企業に限らず、ヨーロッパ、日本、中国の企業などにも認められています。
Industry4.0は、ドイツの産業政策の一環として産学官が連携し、製造業の革新を実現しようという取り組みです。

SIEMENSは、ドイツのIndustry4.0の考え方を強く受けており、ドイツ全土の中小企業の工場を1つの基盤としてまとめ上げるプラットフォームを目指しています

https://wisdom.nec.com/ja/technology/2016012901/index.html
この第4次産業革命は、ものづくり大国と呼ばれてきた日本にとっても大きなインパクトを持っています。
しかし、日本の製造業において、他国と比較してIoTの導入をはじめスマート工場化が進んでいるとは言い難いようです。
もし日本がこの波に乗り遅れた場合、ドイツに大きく水を開けられてしまう懸念があるでしょう。
SIEMENSの戦略
SIEMENSといえば、ガスタービンメーカー世界3強の一社として名をはせてきました。
2020年に創業172年目となるほど歴史と伝統のある企業で、グループ全体で売上約10兆円、従業員約38.5万人の巨大な企業グループです。
デジタル化の必要性を強く感じた同社は、2000年代からソフトウェアを中心とした様々な企業を買収し、当時多くの新聞で「なぜ全く関係ない企業の買収をするのか」と批判が絶えませんでした。
しかし、数年後「これほど素晴らしい戦略を打ち出した企業はない」と手のひらを返したように賞賛されるようになりました。
2007年以降総額7000億の投資をしてソフトウェア会社を買収し、近年ではMentor Graphics(メンターグラフィックス)を買収したことにより投資額の総額は1兆円にものぼります。
今まで主力であったガスや電力事業ですが、パリ協定で環境意識が強まる風潮において、縮小すると発表。
長い年月をかけてソフトウェア会社を次々に買収してきた同社は、ついにスマートインフラやデジタル産業に主力事業をシフトしていきます。

SIEMENSは、2018年の時価総額においてGEを逆転しました。GEより11兆円超の差をつけました。
2019年9月期にSIEMENSのデジタル産業部門は約20%の利益率を叩き出し、6年でほぼ倍増しています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66227560T11C20A1TJC000/
強力なIoTプラットフォーム製品:MindSphere
現場で取得したデータを解析して、傾向を見える化するIoTプラットフォームである「Mindsphere」は2016年にサービスが開始となり、生産現場で活用されています。生産ライン中の設備それぞれの稼働率、工場間での生産状況、生産効率の違いなどを一目で分かるようにするサービスです。
MindSphereのコアコンセプトは、「産業用IoTを実現するためのソフトウェアや接続性などを実現する」として、下記の3つが重要とされています。
- オープン
- コネクティビティ(接続性)
- スケーラビリティ(拡張性)
この中で、SIEMENSは、解析や見える化の対象となるデータを現場から吸い上げてクラウドに送る「コネクティビティ」の部分が最も重要なものと位置付けています。
SIEMENSは電力、産業機器、医療、情報通信、交通・運輸などの広範な市場の現場を顧客に、170年以上の歴史を持っています。
その間に培った現場への理解とノウハウが強みとしてあるため、コネクティビティで差別化ができると述べています。
SIEMENSのマインドスフィアを含むデジタル部門の営業利益は、18年4~6月期に65%増の5億8700万ユーロ(約770億円)。
2020年7~9月の利益率は一過性の要因を除くと13.8%となりました。
これはGEの5.6%、日立の5.7%を大きく上回りました。新型コロナウイルス下でも、粘り強さを見せ、2020年9月期通期の決算は売上高・利益とも小幅減にとどめました。
MindSpehereの顧客
MindSphereは以下のような場面で使われます。
- 機器メーカーが機器のデータを収集するデータ基盤として使うケース
- 工場および生産ラインなどを、運営するエンドユーザーが現場のデータ収集に活用する
MindSpehereが日本での導入加速
Azureが「Azure Stack」などでオンプレミス環境との連携を強化しました。
これによって、「データは工場内から出したくない」けれども「MindSphere上で稼働するアプリケーションを使いたい」という場合にも対応が可能になりました。
日本では2019年からこのサービスを受けられるようになります。
このようなSIEMENSの取り組みにって、日本で導入が加速しています。
「導入企業数は現状2桁ですが、1年間で5倍以上に増えている」とシーメンス(日本法人)の専務執行役員の島田氏が述べました。

https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/cdc/extra/1111614.html
GEの低迷
GEのカリスマ経営者であったジャック・ウェルチ氏が力を注いだ金融事業は2008年の金融危機で巨額の損失が生じ、イメルト氏は負の遺産の処理に追われることになりました。
この時期からGEの経営は低迷し始め、イメルト氏時代の16年間、売上高はほとんど伸びていませんでした。

https://www.shimaji-amekabu.com/entry/america/ticker/ge
そこで社運を賭けたサービスとして登場したのがIoTプラットフォーム「Predix」でした。
GEとSIEMENS両社を逆転させたのは何だったのか
Predixは、産業機器などハードウエアをセンサーを使用してインターネットにつなげ、得られるビッグデータを分析し、工程管理やメンテナンスなど顧客サービスにつなげる構想でした。
「2020年にソフト事業の売上高を150億ドルにし、ソフト会社として世界トップ10に入る」と宣言し、製造業からデジタルサービス業への転身を図ろうとしました。
しかしこの転身を図ろうとしている間に、最大のライバルであるSIEMENSは地盤を揺るぎないものにしていきます。
SIEMENS版のPredixは、今ではPredixよりプレゼンスは高いとされています。
それではなぜ、GEはSIEMENSに追い抜かれてしまったのか。その要因が何なのかを次で見てみましょう。
GEの「Predix」が失敗した理由
GEは産業機械を使う自社顧客にも他社顧客にもPredixを売り込みましたが、顧客からの反応は「既存システムからわざわざ乗り換えるメリットを感じない」というものでした。
プラットフォーマーを目指していたGEにとって、この反応は予期せぬ壁でした。
Predixはそもそも自社向けに設計されており、GE製のハードと抱き合わせのビジネスを狙っていたのです。
しかしこのことは「外部企業が使いにくい」という短所として突き付けられ、ある日系メーカーの幹部は「GEは自社のために開発したプラットフォームを押しつけるような商法そ取っていた」と述べています。
このことで分かるのは、Predixが失敗した要因は「顧客視点が欠けていた」ということではないでしょうか。
MindSphereの成功の理由はユーザーファースト
SIEMENSのMindSphereは、ユーザーファーストを掲げています。そのため、MindSphereのシステム利用だけにとどまらず、ベンダーとのパートナーの間で協定を結びながらプラットフォームの機能を充実させることが可能です。
「顧客のかゆいところに手が届くサービス」を心がけています。
この点において、Predixと差がついてしまったのでしょう。このパートナー提携企業一覧を見ると、顧客が他社のシステムと併用してMindSphereを使用できることが分かります。

https://image.itmedia.co.jp/l/im/mn/articles/1906/25/l_sp_190625siemens_06.jpg
また、コストをかけずに導入できることも魅力となっています。
IoTバリュープランの一番安価なプランは、「IoTバリュープランS」と呼ばれており、4万円から使用できるのも顧客にとっては嬉しいサービスです。
日立のLumada(ルマーダ)
売上収益増のLumada
株式会社日立製作所は、33万人を擁する10兆円企業でありながら、東芝や各社には見られない総合力と、同社に根付く「ベンチャー精神」によって技術力を磨いてきました。
2020年度上期(4~9月)の連結業績において、売上収益が前年同期比10.9%減の3兆7600億円、営業利益(調整後)は同39.2%減の1807億円という結果でしたが、Lumada事業は、売上収益が9%増となりました。
新型コロナウイルスの影響により航空や自動車、ビル関連の需要低迷が見込まれているため、22年3月期にLumada事業の売上高営業利益率で10%超という目標を掲げています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59766990Z20C20A5X13000
最近では、AIやデータ分析を使用したソフトウエアをクラウドを通じて提供する「SaaS」事業を持つ「フュージョテック」という企業を買収しました。このことによって、アジア地域で1万社を超える顧客基盤を手に入れることに成功し、SaaS事業のサブスクリプション(定額課金)サービスなどを日本や北米などでもサービスを展開していきます。
しかし、最終年度の目標に近づくには、さらなるM&Aが必要とされており、2022年3月期までに、Lumada事業で8000億円超の投資枠を設けています。
Lumadaの強力な武器であるサイバーセキュリティ
GEやSIEMENSと同じように、第4次産業革命の担い手を目指す日立製作所。
2017年秋、GEデジタルの最高執行責任者を務めたブラッド・スラク氏を引き抜いています。
しかし、だからと言って「GEと同じやり方はしない」と経営幹部は述べ、プラットフォームのソフト導入先を広げるだけでなく、付加価値として新たなデータ分析方法やサービスの開発も重視していくとしました。

近年、さまざまな用途でIoT導入が進んでいますが、サイバー攻撃の手口が巧妙化しています。
企業のITシステムに限らず、機器や設備などの管理を行う制御システムもその脅威の対象になっています。
しかし、日本では、セキュリティ担当者が不足していることが問題となっており、育成が喫緊の社会課題となっています。
日立はIoTプラットフォームサービスを提供する企業として、特にセキュリティに対策に力を入れています。
株式会社日立製作所、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト、株式会社日立ソリューションズの3社は、2019年12月9日に「日立サイバーセキュリティセンター」を開設すると発表し、日立グループにおける「高度セキュリティ人財」の育成と、サイバーセキュリティ研究を目的として設立しました。
高度セキュリティ人財は、日立グループ内外で急増するサイバー攻撃に対して迅速かつ適切な対応力の強化を目指しており、2022年3月末までに1万人規模で育成する計画を示していました。

https://www.hitachi.co.jp/IR/library/integrated/2019/ar2019j_19.pdf

https://www.hitachi.co.jp/IR/library/integrated/2019/ar2019j_19.pdf
日立グループの提供するIoTサービスは、中小企業向けのサービスというよりは大企業の工場や社会インフラ(鉄道・スマートシティ・発電所など)の領域に特化しています。
そのため、このような基幹がサイバー攻撃を受けてしまうと、社会インフラに影響します。
日立グループは、インフラに関わる大企業が顧客を持っているという点で、セキュリティレベルを極めて高く維持しているため、各社のIoTプラットフォームと比較すると日立のLumadaの方がセキュリティレベルは極めて高水準と考えます。
最後に
IoTプラットフォームのサービスを提供する、SIEMENS、GE、日立の製品の特徴をご理解いただけましたでしょうか。
この3社の戦いからGEは完全に降りてしまうのでしょうか。
今後は、SIEMENSと日立の間でシェアの競い合いが本格的に始まるでしょう。
日立は日系最大手のコングリマリット企業としてサービスにおけるセキュリティを武器に、今後より一層グローバル市場に乗り出していくことが期待されます。
<参考>
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXT/19/rohm0201/
https://blogs.itmedia.co.jp/itsolutionjuku/2016/09/predixfield_system.html
https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1285915.html
https://www.news-postseven.com/archives/20170307_498843.html/2
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59791
https://ascii.jp/elem/000/001/177/1177347/2/
https://iiot.jp/iiot_specials/is-0030/
https://blog.rflocus.com/iot-platform/
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/17/032400102/032400001/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00065/00128/
https://summarytoday.jp/2019/08/18/ge-stock-price-low/
https://www.techcrowd.jp/relatedweb/iotplatform/